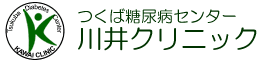活動報告
2024年11月20日(水)豊里交流センターにて、「おかずも野菜もバランス良く!シンプルなパンの三変化」をテーマに、桐の木会会員の方からの要望をもとにパンを使って調理実習を行いました。組み合わせや食材の置き換えを工夫し、美味しく栄養バランスの整った、菓子パンや調理パンに代わる「パン食」を、ということで「ミニハンバーガー」「フレンチトースト」「ツナカレーのオープンサンド」「根菜のトマトスープ」「春菊のサラダ」を作りました。調理後は管理栄養士による「バランスの良いパン食を」の講義も行いました。患者さんからは、「簡単にできて美味しかった」「3種類のパンは食べ応えがあって満足感があった」などの感想をいただきました。次回は1年後となりますが、今後も皆様の参考になるような献立を提案していきますので、ぜひご参加ください。
2024年6月2日(日)に茨城県糖尿病協会主催の『第26回歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー』に当院より会員外の方も含め9名の方が参加しました。
午前は「糖尿病腎症の食事について」「糖尿病腎症と尿検査」「糖尿病と慢性腎臓病について」のお話を聞き、腎臓の働きや運動、検査の必要性、糖尿病性腎症は透析導入疾病の1位であることなど学びました。
午後は2組に分かれ霞ヶ浦総合公園でコース図に従ってチェックポイントを探し、クイズを解いたり、ストラックアウトをしたりしてウォーキングしました。残念ながら途中雨に降られ中止となりましたが、体調不良者も出ず、参加者同士の交流を深めとても楽しい会となりました。
2024年3月27日(水)に福島県三春町に日帰り旅行へ行ってきました。三春町の町名は、春にウメ、サクラ、モモの花が一時に咲くことに由来しているそうです。残念ながら、楽しみにしていた桜の開花とはなりませんでしたが、歴史と文化の城下町を学びながら散策してきました。昼食には、幻の三春そうめんや奥州三春の味の油揚ほうろく焼などをいただきました。たくさんの患者さんに参加していただき、普段できない会話も楽しむことができました。皆様がまた参加したいと思うようイベントを企画していきたいとおもいますので、よろしくお願い致します。
2023年11月29日に桜総合体育館にて桐の木会「運動の会」を開催しました。今回は、「健歩力を高めよう!」というテーマで、当院の運動教室を担当している野口克彦先生に講義をしていただき、実践も行ないました。速く歩くほど寿命が長くなるという研究報告があり、ゆるやかなウォーキングとややきついウォーキングをそれぞれ2分ずつ組み合わせて5セット行い、心拍数が「180-年齢」の強度になることが大切であると教えて頂きました。実践してみると、20分でも良い運動になり、毎日繰り返すことで、体力や筋力アップに繋がると実感しました。
2023年9月27日(水)豊里交流センターにて、「代替食を使ったメニュー」をテーマに調理実習を行いました。お肉の代わりに低カロリー・低脂質・高食物繊維の「大豆ミート」を使用しました。患者さんより郷土料理の要望もあったので、今回は沖縄料理を取り入れた「タコライス」「ゴーヤチャンプル」「もずくスープ」「パインゼリー」の献立を考案しました。調理後は管理栄養士による「代替食の活用方法について」の講義も行いました。今回4年ぶりの調理実習だったのですが、皆さんとても手際がよくてスムーズに進行しました。患者さんからは「大豆ミートを食べるのは初めてだったけど、お肉みたいで美味しい」「お肉よりも柔らかくて食べやすい」などの感想をいただきました。次回の調理実習は冬頃に行う予定ですので、皆様のご参加をぜひお待ちしております。
2023年6月11日(日)にコロナ禍で長らく開催できていなかった茨城県糖尿病協会主催の「歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー」が4年ぶりに開催されました。当院からは会員外も含め7名の方が参加し、死因の上位を占めるがん・心臓病・脳卒中の予防方法や、介護保険の基礎といった講演を聞くことができました。残念ながら雨天により午後に予定していたメインイベントのウォークラリーは中止となってしまいましたが、脳を活性化させる講演では、音楽に合わせて手を動かす運動を紹介していただき皆で盛り上がりました。また、講演後は糖尿病や茨城県に関する問題を皆で解いたり、運動療法士の先生からストレッチや室内でできる運動を教えていただいたりして、とても充実したイベントとなりました。
次回の桐の木会は令和7年3月頃に日帰り旅行を予定しています。状況により中止になる場合には改めてお知らせいたします。
過去の活動報告
 pdfファイルとして閲覧ができます。
pdfファイルとして閲覧ができます。